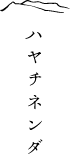<いのち>の源流の輝き —— 宮沢賢治を通して

忍峠にて
六月、柳田國男が遠野の附馬牛(つきもうし)に入るときに通った忍峠(しだとうげ)を抜ける。六月の遠野には珍しく夏のような一日。
生命を漲らせた植物は、私たちを車ごと呑み込んでしまいそうな勢いだ。
このまま呑み込まれてしまいたい恍惚と、呑み込まれてしまう畏れとがないまぜになるなか、あゝ賢治はこんなに圧倒的な自然の中に身を置いたのかと、突然肚に落ちた。
しばらく遠ざかっていた宮沢賢治の著作を手にしたのは、七月の「ンダ部」のトークイベントがきっかけだった。ゲストの写真家・津田直さんがテーマに選んだのは「ほんたうのいのち—鹿踊りを巡る旅」。
津田さんは、Reborn-Art Festival 2019で鹿を巡る一連の作品「やがて、鹿は人となる/やがて、人は鹿となる」を発表。その後、舞台となった石巻の牡鹿半島を起点 に北へと旅を続け、東北地方に伝わる鹿踊り(ししおどり)を辿り、宮沢賢治の童話「鹿踊りのはじまり」に出逢う。その夜のトークイベントは、Reborn-Art Festival 2019 での作品発表から2年をかけて編まれた冊子「やがて、鹿は 人となる/やがて、人は鹿となる」の朗読からはじまった。
「あなたのすきとほつた ほんたうのいのちと はなしがしたいのです」
冊子はこの一文からはじまる。
それは、宮沢賢治の童話集「注文の多い料理店」の「序」と響き合っている。
わたくしは、これらのちいさなものがたりの幾きれかが、おしまひ、あなた のすきとほつたほんたうのたべものになることを、どんなにねがふかわかりません
「注文の多い料理店」/「序」
賢治の作品において「すきとほつていくもの」はしばしば過去や未来の存在が ここに立ち現れることを意味していると言われる。そのことを通して詩人は 「感官の遥かな果て」(「風の偏倚」)へと行き着くのだ。
感覚器官の遥かな果て、言葉で秩序づけられた枠組みや規範や、時間や空間さえ超えた向こう側は、賢治にとってどんな世界なのか。
私は、見田宗介さんの「宮沢賢治 存在の祭りの中へ」を教科書に、賢治の世界感覚について学んだ。
拙い理解ながら、これを記そうと思い立ったのは、見えざるものや言葉で説明できないもの、数値で捉えられないもの、いわば言葉で秩序づけられた「概念化」の向こう側にある世界への感度が、私たちの活動には必要であること、そして何より、現代の孤独な<いのち>への希望を、賢治の生命観のなかに見つけることができたからである。
<いのち>が還る場所の輝き
日本人の精神の古層には「今ここにある<いのち>は仮のもので、亡くなれば大元にある大きな<いのち>の流れに還ってゆく、そして魂は浄化される」、そのような死生観があるという。
魂が還ってゆく「大元の大きな<いのち>の流れ」は、賢治にとって「死のむこうにまでいちめんに生の充溢した世界」「存在の地の部分にこそみちあふれているいちめんの輝きと光」の世界であるように思えた。
そのことを見田さんは、たとえば「おきなぐさ」という童話の中に見出している。
“丁度星が砕けて散るときのやうにからだがばらばらになって一本ずつの銀毛はまっしろに光り、羽虫のやうに北の方へ飛んで行きました”
「おきなぐさ」
おきなぐさの銀色の綿毛たちの旅立ちには、「いつかあたらしいおきなぐさたちの生命の中によみがえる」<いのち>の連鎖の輝きがある。
先に記した「存在の地の部分」とは、「にんげんの身を包んでいることばのカプセルとしての『わたし』の外に広がる世界、私たちが言葉によって秩序づけ、概念化する前の生のままの自然と言うべきもの」を指している。賢治はそこを輝きと光に溢れたものとして感得している。
個としての「わたし」とこの生の自然との関係を見田さんは、ヘブライ・キリスト教との比較で説明してくれている。
それは、ハヤチネンダが考える「現代の<いのち>の孤独」にも通じるものであることに気付かされた。
長くなるが、ヘブライ・キリスト教を突き詰めることでヨーロッパ近代精神を用意した思想家カルヴァンについて概論した部分を引用する。
「<神>によって祝福され秩序づけられた『世界(コスモス)』の内側だけが意味のかがやきをもつものであり、この『世界(コスモス)』の外にあるもの、生のままの自然それ自体の如きものは、罪深いもの、少なくとも無意味なものである。そうであればこそカルヴァンは、この偏在する闇の中への失墜を恐れ、<神>の恩寵による存在の奇蹟をその瞬間ごとに求め続けねばならなかったのだ。」
今、「<意味の光源>としての神それ自体を失った」私たちには、「偏在する宇宙の無意味のただ中につかのま存在し、やがてかくじつに虚無の中に没してゆくのだという、荒涼たる世界感覚だけが残される」
現代に生きる私たちの<いのち>の孤独は、大きく捉えればこのような世界感覚から生じていることに合点がゆく。
しかし、賢治のそれは、自我の闇と光が反転しているのである。
おれはひとりの修羅なのだ
春と修羅
「<修羅>のイメージへと集結する賢治の自我は、暗いようにみえる。けれどもわたしを驚かせるのは、この修羅をとりかこむ世界、存在の地の部分の如きものの、まばゆいばかりの明るさである」と見田さんは言う。
「ヘブライ・キリスト教世界出自の自我の原型が、いわば偏在する闇の中をゆく孤独な光としての自我というべきものであることとは対照的に、ここでの修羅は、いわば偏在する光の中をゆく孤独な闇としての自我である」
そして、見田さんはこのようにこの論を結んでいる。
「わたしたちが『自我』のかなたへゆくということを、ひとつの解放として把握する思想を支えることができるのは、このような世界感覚だけである」
「自我のかなた」とはどのような場所なのか。
感官の遥かな果てへ
感ずることのあまり新鮮にすぎるとき それをがいねん化することは きちがひにならないための 生物体の一つの自衛作用だけれども いつでもまもつてばかりゐてはいけない
青森挽歌
見田さんは言う。
「<がいねん化する>ということは、自分のしっていることばで説明してしまうということである。たとえば体験することがあまり新鮮にすぎるとき、それは人間の自我の安定を脅かすので、わたしたちはそれを急いで、自分のおしえられてきたことばで説明してしまううことで、精神の安定をとりもどそうとする。けれどもこのとき、体験はそのいちばんはじめの、身を切るような鮮度を幾分かは脱色して、陳腐なものに、『説明のつくもの』になり変わってしまう」
賢治は、「人間の感覚器官でとらえられるものだけを信じる『明晰さ』というものを批判して、人間の感官がそれじたい限界のあるものであることを指摘している」
よく知られているように「青森挽歌」は、亡くなった妹のとし子の存在の行方を求める旅であった。
それらひとのせかいのゆめはうすれ あかつきの薔薇色をそらにかんじ あたらしくさはやかな感官をかんじ
青森挽歌
見田さんは、賢治はとし子のいる場所をこのように捉えたのだと考える。
賢治は、「そらいっぱいの光の散乱反射する空間として感覚することのできる<あたらしくさはやかな感官>の存在することを信じていた」。
「いいかえればわたしたち自身の生が、<意識ある蛋白質>としてのつかのまの年月をこえて、存在の光の中に共に生き続けてあることの認識を獲得しようとしていた」。
見田さんはさらに言う。
「<力にみちてそこを進むもの>だけが、自分の「世界」に裂け目を作って未知の空間に出で立って行くことができる。そこは<がいねん化>のはたらく以前の、すべてがあるごとくにあり、かがやくごとくにかがやいてある場所である。賢治ととし子、生きているものと死んでいるもの、人間とあらゆる生命、人間とあらゆる非生命とをわけへだてている障壁をつきやぶる武器」、それこそが「感官の遥かな果て」へと馳せる力なのだと思う。
そして、それは私たちの身のうちにある。
(文・宮田生美/ハヤチネンダ)
【出典】
■「宮沢賢治 存在の祭りの中へ」 見田宗介著 (岩波現代文庫)
■「 やがて、鹿は人となる/やがて、人は鹿となる」 津田直著 (handpicked)
■「注文の多い料理店」 宮沢賢治著 (日本近代文学館)
■「校本宮沢賢治全集」 (筑摩書房)
※引用は「宮沢賢治 存在の祭りの中へ」による。